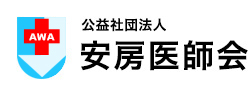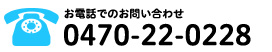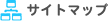巻頭言 Vol.54 No.3 2018
巻 頭 言
安房医師会理事 小田常人
4月より6年に一度の診療報酬と介護報酬の同時改定が施行されました。今回の改定は団塊の世代が75才になる2025年とそれ以降の社会経済の変化への対応に向けた道筋を示す、実質的に最後の改定となる重要な節目だと言えます。
まず改定率に関しては、診療報酬本体部分が0.55%引き上げられた一方で、薬価の大幅な引き下げにより全体としては1.19%のマイナス改定となり、この傾向は今後も続くことが予想されます。重点課題としては、地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進が示されており、関連する様々な項目が見直されました。外来医療の機能分化とかかりつけ医機能の推進を目的に、紹介状なしの大病院受診時の定額負担の対象範囲の拡大、「地域包括診療科・加算」、「認知症地域包括診療科・加算」がそれぞれ2段階となり、その医師配置に関する要件が緩和されています。
在宅医療についても評価が見直され、算定項目が新設されました。他の医療機関から訪問診療の依頼を受けた複数の医療機関が評価の対象になる、「在宅患者訪問診療科Ⅰ.2」が新設され、様々な病気を同時に罹患している患者が、専門の他の病院を受診したい場合なども連携が容易になります。また、在宅療養支援診療所以外の診療所が、他の医療機関と連携し、24時間の往診体制及び連絡体制を構築した場合に加算される「継続診療科加算」が新設されました。これによって、在宅医療に従事する医師の負担が軽減されるとも考えられます。さらに、要介護2以上、認知症高齢者の日常生活自立度でランクⅡb以上の患者など、状態に応じたきめ細やかな訪問診療に対し加算される「包括支援加算」も新設されます。これまで、在宅医療に対する、診療報酬上の評価があまり十分ではありませんでした。そのため、高いニーズにもかかわらず、在宅医療を行う診療所はそれほど多くはありませんでした。今回の改定で、評価が見直され、新規参入が進むことが期待されます。
安房地域でも、地域包括ケアシステムの構築にむけて、医師会、行政が中心となって議論が行われています。今回の診療報酬改定により、在宅医療を積極的に行う診療所が増えることにより、病院、施設、との連携もスムーズとなり、より良いシステムができると思われます。私も微力ながら、協力していきたいです。
巻頭言 Vol.54 No.2 2018
巻 頭 言
新年度のスタートにあたり
安房医師会理事 亀田信介
2018年度は、診療報酬と介護報酬の同時改訂が行われると同時に、新専門医制度のスタート、医師の働き方改革など、医療界の未来に大きな影響をもたらす年になるでしょう。
診療報酬制度については、報酬額よりも、今後の医療施設や介護施設のあり方を含む医療・介護連携をはじめとした地域包括ケアに対する方向づけを明確に打ち出すという意味合いが強いと思います。
医師の労働問題は、政府の働き方改革という方針に沿って突然大きな問題としてクローズアップされました。労働基準監督署が医師の労働時間や時間外手当の支払いをめぐって、多くの医療機関の立ち入り調査を行っています。しかし実際問題として、医師の労働時間については定義も測定手段もありません。若手医師たちは、院内で多くの時間を自己研鑽のための学習や研究に使っています。そもそもさまざまなキャリアや価値観の異なる医師たちと時間を共有することがいかに貴重な学びの場となるか、医師にとっては周知のことです。
また厚生労働省は、日本の国民皆保険制度は低コスト・高品質の世界に誇れるシステムだと威張っていますが、これを可能にしてきたのは医師の多大な自己犠牲によるものです。そこにむやみに労基の理論を持ち込めば、地域の救急医療などは真っ先に崩壊します。
現に安房地域でも富山国保病院と鋸南国保病院に労基の調査が入り、医師の長時間労働に対する指摘を受け、今後の運営方針を模索し苦しんでいます。しかし、安房地域の3つの自治体病院は、それぞれ3名の常勤医師しかいませんから、労基の指導を遵守したら、救急どころか、病院としての最低条件である24時間、365日医師を常駐させるという規定を守ることすらできません。
一方、今年から新専門医制度がスタートするため、基本診療領域における都道府県ごとの応募状況が見えてきました。日本専門医機構は、地域偏在の問題は無いと主張していますが、首都東京への一極集中と診療科間の偏在は明らかに加速しています。さらに、今後は研修病院でないかぎり、専門医研修を修了する前の若手医師の確保はもちろんのこと、指導医の確保も極めて困難になると思われます。このような状況の中、安房地域の医療・介護サービスを守ってゆくためには、合理的で持続可能なシステム改革が必要です。例えば急速に進歩すると予想される情報通信技術を活用した遠隔診断や遠隔診療、さらに人工知能(AI)による画像診断や臨床診断等のシステム構築や、地域医療連携推進法人等による施設類型や連携の抜本的見直しなどが考えられます。
医療は地域の重要なインフラです。これを守り、少しでも効率的で質の高いサービスを提供することが私どもの使命と考えます。
巻頭言 Vol.54 No.1 2018
巻 頭 言
安房医師会 会長 小嶋良宏
新年明けての冒頭の挨拶文は失礼ながら割愛させていただきます。
黄金比は、1:1.618、1÷1.618=0.618、61.8%としておこう。冲中先生の最終講義での有名な数字は14.2%、言い換えれば85.8%。大学での成績の評価は、単純に優、良、可、不可。ご承知の通り優は80%(80点)以上の点数。もちろん可は60%(60点)以上であり、黄金比と可は似たような数字である。
我々の任期も残すところ6ヶ月になってしまいました。やり残したこと、継続して行っていかなければならない事業など書ききれないほどありますが、3月に行われる総会で発表する事業計画案をこの新年号に記載します。
主文、地域医療について行政その他関係する機関と議論、連携し永続的に考えていく。
地域医療を守ることと、地域住民の健康を守ることは全く同義語と考えます。医療施設がない場合、どうやって病人を治療し、助けるのでしょうか?医療施設がなくなってしまっては住民の健康を守ることはできません。日本の、いや世界の国々を構成する住民一人の命を守ることがその地域、国、世界を守ることに通じます。医療なくして住民の健康を守ることなど不可能です。
鴨川市国保病院建て替えの件は、地域医療を守るまさにその第一歩です。この件は鴨川市だけでの問題ではなく、広く安房地区の医療問題としてとらえねばなりませんので学識経験者、県庁、保健所長や行政担当者といった方々と会合をしてきました。理由は、鴨川市以外の住民も受診、災害があった場合には他地区の住民も利用する中核病院として機能することにもなりますし、他の公立病院もいずれ建て替え問題に直面しますので今後も多方面と協議をする必要性があるからです。
この事案をきっかけに地域医療を考えていく機とし、話し合いを重ね、公立病院だからこそできる医療、他の公立病院の見本となる運営や内容、私立病院や医院と共存共栄し、素晴らしい医療を提供できる施設となることを期待していますが、医師不足など解決しなければならない問題があり、その実現には多くの協力と理解が必須です。
学校職員に対する眼科関連の検査法や疾病の講義、父兄や児童、学童に対する健康教室や啓蒙なるものを組織的に行えなかったことは未だに悔いが残ります。教育委員会には何回か相談を持ちかけましたが、いまだかつてそれは実現されていません。安房郡市の一部の小学校では、禁煙教室と称し喫煙の健康被害についての講演は行われているので、決して実施率はゼロではありませんが、組織的に実施できなかったことは大いに反省しています。松戸市医師会では、まちっこプロジェクトと称し子供のために出前講座、言い換えれば健康や病気に関する講演会を組織的に行っています。今後は、松戸市医師会を見習い、未来の日本、いや世界を支える子供のための何らかの健康や病気に関する啓蒙事業を組織的に実行しなければなりません。
在宅医療、介護と医療の多職種連携、協力に関しても今後も継続して行っていきます。
幸いにも、この分野に秀でている理事、会員や行政の協力もあり、微々たる歩みですが、各関連施設と顔の見える関係は構築され、さらには信頼関係も育ちつつあります。しかしながら、介護関連施設の横のつながりがまだまだ弱いように見受けられますが、担当理事が奮闘しており、横のつながり、ネットワークを構築中であり今後に期待します。
災害医療に関しては、願はくば地震は起きて欲しくないし、津波にも襲われたくないのが本心でありますが、いつなんどき起きるのか誰にもわかりません。大雨による災害発生も懸念されます。このような災害発生時においては、行政との協力のもと医師会はできる限りの協力することは言うまでもありません。最近、市の担当者と小さな会合を持ち、そこで出た意見をまとめ、医師会理事会に提出、審議しさっそく実行に移すことになりました。
行政と医師会はクルマの両輪のごとく協力し支え合う必要がありますので、定期的に行政と会合を持ち、市の考えを聞き、情報を共有し住民のために活動していきます。
さて、我々が行ってきた活動の評価は如何に?可であってほしいがその判定は歴史に任せ、次期理事の方々には黄金比のようにバランス良いデザインの如く、バランス感覚が優れた運営をする安房医師会理事会とな ることを願うとしよう。
巻頭言 Vol.53 No.6 2017
巻 頭 言
安房医師会 理事 杉本雅樹
安房の未来は?
私の巻頭言が掲載される頃には、新しい日本のリーダーが決まっていることでしょう。
締め切りに追われ(正確には締め切り過ぎ)、ふとテレビを点けてみたらnews23で党首討論をやっていました。なんと、今回の解散は、“迫りくる危機のための解散!!、北朝鮮問題と少子高齢化問題だ!!”と安倍首相がおっしゃっていました。へぇ~、そうだったんだ!!(当然モリトモ・カケイは関係ありません)これが私の率直な感想です。
さて、迫りくる危機、少子高齢化!!高齢化に関しては他の先生にお譲りし、私は少子化について少々お話しできればと思います。
以下の表は、ここ15年間の安房郡の出生数です。全国的には毎年2%の出生数減ですが、安房管内は約5%の人口減です。また、お隣の上総地区(富津、君津、木更津、袖ケ浦)のH27年の出生数の合計は、2,406人です。みなさまいかがでしょうか?

当法人は産婦人科有床診療所なので、診療報酬の約80%は出産に付随するものです。そして、364日24時間助産師の対応、どんな時でも帝王切開できる体制を整えているため、人件費は相当なものです。
話は変わり、内閣府のホームページによると、地域別にみた医療・介護の余力において、安房は関東で唯一、“医療は余裕、介護は平均レベル”のようです。
これは、既に医療に余裕のある安房地区(あまり潤っていないということか?)において、若年層が激減してくる10年、20年後には、会員の皆様の運営も相当厳しいことが明白であり、今からそれなりの準備が必要であります。
私は、執行部以外の安房医師会の現職理事の中で、最年少にして最長在任理事であります。医師会病院の移譲から現在の体制に至るまで様々なことがあり、その一つ一つが自分の人生観の土台になっています。その安房医師会が今後どうなっていくのか?
私はいまだ最年少理事でもあるので、決して傍観者にならずに可能な限り関わっていこうと思います。最近バタバタしているため、会員の皆様にご迷惑をおかけしている場面が多ございますが、ライフワークの一つとして医師会活動をしたいと思います。どうぞ、よろしくご指導お願いいたします。
安房の未来は明るくなくとも、安房医師会の未来は素晴らしいものにしたいというのが私の思いです。
巻頭言 Vol.53 No.5 2017
巻 頭 言
安房医師会 会長 小嶋良宏
近年、Information and Communication Technologyが発達し、我々が生活していくうえで、それを利用することはもはや切っても切り離すことができない世の中になっているのは否定できないであろう。
特にSocial Network Service(以下SNS)を利用している人々は全世界に存在する。
最近、そのSNSを使ったツールの勉強会に出席したので、その概略について以下に記す。
災害時の安否情報共有アプリ。
その製品はスマートフォン、PCを使っての情報伝達SNSである。家族、企業、学校、グループなどで管理者(権限者)を決め、専用アプリを個人で取得、登録する。登録したメンバーの安否情報を管理者は一覧で確認することが可能なサービスである。
使用方法であるが、スマートフォンの画面に幾つかのボタンが表示される。体の状態を伝える、周りの状態を伝える、これからの活動を伝えるボタンが並んでおり、自分の状況を画面にタッチするだけで、瞬時にその情報が管理者に伝わる仕組みになっている。
たとえばの使い方であるが、医師会が管理者となり、賛同された会員がそのアプリをダウンロード。
災害時には、先に述べたように画面をタッチし、情報を伝達したとしよう。医師会のPCの画面には、各会員が画面を押した時間、地図などが表示される。その情報を参考に、緊急医療体制などを構築することが可能であると考える。
しかしながら、管理者が被災した場合には安否確認ができないだけではなく、機能不全に陥る懸念がある。
このSNSを利用していない会員の安否確認ができない場合、他の方法を使っての確認となるのは言うまでもない。しかしながら大災害のパニック状態時にどのようにして安否を確認するのか、誰が確認するのかは今後の課題である。
医療と介護を担うグループ内での連携のアプリ。
やはり、スマートフォン、PCを使ってのSNSである。
要介護者、在宅患者を中心とした多職種連携ツールであり、ヘルパー、ケアマネ、医師、看護師、薬剤師などがチーム医療をするときの医療介護連携をスムースに遅滞なく行う方法である。
たとえば、医師が往診した時にその患者さんの情報を入力すれば瞬時にチームを組んでいるメンバーに情報が伝わる仕組みであり、いちいち電話をしたりファックスを送ったりしなくて済む。また、情報を共有することにより、同じ質問をしなくて済み、2度手間、3度手間といった無駄を省くことができる。
文字情報だけではなく、その場において写真を撮って送れば体の状態を瞬時にチーム全員が把握することが可能、また災害時には近所の状況の写真を送ることにより被災程度の状況判断にも有用かと考える。
以上2種類のSNSの概略を列挙したが、短所ももちろん存在する。
使用者側の一般的な短所としては、スマートフォンの充電切れ、機器の故障であろうか。サイト側では、サーバーの故障も考えられる。
大きな短所としては、故意またはミスによる情報漏洩である。災害時には、個人の安否情報は個人情報保護法違反にはならないとい考えるが、介護医療関連ツールにおいては患者情報が漏れた場合、最大のプライバシー侵害となってしまう。その情報の管理は厳密でなくてはならない。
また、集められた通称Big Dataを加工し、その情報を特定の企業なりに売りつけビジネスとしてしまうかもしれないが、それを心配しても埒があかないのが現状である。
いずれにせよ、上記の2点はただの情報伝達ツールであって、最後には人間対人間の関係が最重要になる。
安否情報共有アプリは、それを登録している人々には何らかの恩恵があると考えるが、全住人が登録するのは不可能である。もし、災害時に登録していない人々が不明になった場合には住民の方々、特に隣近所の方々、郵便、宅急便や新聞配達の方々などの協力がなければ安否確認は不可能であると考える。
医療介護連携アプリも同様、患者さんと我々の関係が良好でなくては信頼関係を築けないし、信頼関係あっての診療である。このようなツールをただ使っただけでは信頼関係は構築不可能であり、信頼関係を作るのは人間、ツールではないがしかし情報漏洩されたデータを悪用し信頼関係を壊すのも人間である。
将来、このようなツールが蔓延、溢れた時に大事なのは、得られた情報に飲み込まれるのではなく、情報を取捨選択し利用する能力であり、我々がツールに使われるのではなく、使いこなす能力であり、人間が主、ツールは従、情報を制するものが、、、、、、、、、。
巻頭言 Vol.53 No.4 2017
巻 頭 言
安房医師会 理事 石井義縁
平成30年度から実施が予定されているであろう、地域包括ケアシステムの構築が各自治体で進められている。言い換えれば、各自治体で、その地域にあったやり方で何とかせよということである。さらに、国は在宅医療から看取りに向けた動きを加速させている。在宅医療から看取りは、住み慣れた自宅で、庭の草木でも見ながら安らかに、天寿を全うすることが本来あるべき姿だと言わんばかりである。2012年の内閣府調査では、最期を迎える場所に自宅や老人ホームなどを希望した人が6割を超えているという。しかしながら、実際には病院の看取り率が78.6%で、自宅や老人ホームでの「地域看取り率」は21.4%というデータもあり、希望と現実に違いがある。また、介護疲れ、介護負担により、弱者に手をかける報道が少なくない。新聞報道によれば、2013年以降、高齢者介護を巡る家族間の殺人や心中などの事件が、少なくとも179件発生し、189人が死亡している。加害者も60歳以上が6割を越えており、65歳以上の介護者の約3割が「死んでしまいたい」と感じたことがあり、4人に1人が、うつ状態が疑われるというデータもある。
また、設備投資を最小限に留め、在宅医療専門の診療所ができ、その恩恵を受けようともしている。そもそも、医師はその時代の国の研修システムにはめられ、医師としての経験をつむ。在宅診療の専門医などいない。国として総合診療医の育成が進められているが、現在議論中の総合診療医がすべてを網羅できるはずもなく、「総合診療医」という名が一人歩きしてきたようにも感じる。我々医師は、過去の経験に基づき、その中で、可能な限り最高の医療を提供するに尽きるのである。
このような流れのなか、最期をどのように迎えるかは、本人の意思のみならず、介護者を含む家族の状況にも大きく左右されるのであり、兎にも角にも在宅医療をすすめることに、少々疑問を感じる。
小生の老後は、どのような体制に乗せられていくのか見当もつかないが、周囲に迷惑をかけないようにソフトランディングしたいと思う今日この頃である。
巻頭言 Vol.53 No.3 2017
巻 頭 言
安房医師会 副会 竹内 信一
最近、準?高齢者であることを自覚し始め、また昨年思わぬ大病(脳動脈瘤)を患ってから、今まで気にならなかった周りの事、世の中の事が気になるようになっている今日この頃です。そこで、そんな中でも特に気になる二つの事、一つは言葉の持つ重み・意味の重要さ、もう一つは出処進退について私見を交えて述べてみたいと思います。今年、アメリカでトランプ大統領が就任して以来、就任前からもですがマスメディアとのやり取りを見聞きしていると、言葉の重み・意味の重要さがないがしろにされている気がしてなりません。マスメディアで発表されたことに対して、alternative facts:もう一つの事実と称して「ウソ」の言い換えをしていると思います。post-truth:事実の軽視としか言いようのない状態です。
一方、日本においても顕著な例として南スーダンにおける自衛隊のPKO活動について、戦闘地域で行われているにもかかわらず、戦闘ではないという詭弁を使っている現状があります。その他、小学校道徳の教科書検査の結果、「我が国や郷土の文化と生活に親しみ、愛着を持つ」との点から、「パン屋」が「和菓子屋」に変更されたりと、きな臭さを感じるのは私だけでしょうか。極めつけは「忖度」という聞きなれない言葉です。もともとは古代中国の詩集「詩経」の一節で、「他人心有らば予之を忖度す」とあり、意味は他の人に悪い心があれば私はこれを吟味するということであったのが、最近では権力者の顔色を窺い、よからぬ行為をすることを指すようになってしまったようです。言葉の本来持つ重み、意味が捻じ曲げられているのは悲しいことです。
もう一つの気になること、出処進退については簡単に述べたいと思います。3月の大相撲春場所での横綱稀勢の里の逆転優勝を観て感動し、感じたところがあります。マスメディアは怪我をして出場した稀勢の里を「あきらめない心」、「ネバー・ギブアップ」と褒めたたえたが、本当は「知進知退 随時出處」すなわち進むべき時を知り、退くべき時を知り、いつでもそれに従うという信念を持っていたのだと思います。いかなる仕事についていようと、いかなる環境下にあろうと、「知進知退 随時出處」という背骨を持っている人間は強く、動じないのであろう。また、日本には「散り際千金」という退くべき時を知り、それに従って散ることは千金に値するという私の大好きな言葉があります。今後、私も年を確実に重ねていくので「散り際千金」の気持ちを持って生きていきたいと思っています。
巻頭言 Vol.53 No.2 2017
巻 頭 言
安房医師会 専務理事 鈴木 丹
現在、地域包括ケアシステムの構築が急がれております。地域医療構想の計画を立てて、実施する方向性を示さなければなりません。(平成28年4月の時点)千葉県での65歳以上の人口割合は、24.3%で、全国の都道府県で、6位です。更に安房郡市を見れば、鋸南町は44.0%(県内2位)、南房総市は42.4%(県内3位)、館山市36.7%(県内8位)、鴨川市36.2%(県内11位)と既にかなりの高年齢化が進んでいます。思い出すことがあります。平成28年1月の安房医師会・学術講演会で、あおぞら診療所の川越正平先生の講演を聞きました。題名は「老いても病んでも地域で暮らし続けるために」で、千葉県松戸市の現状を懇切丁寧に以下のように話されました。
・医療介護連携と多職種協働
・地域デスカンファレンス
・多職種が一堂に会する会議
・行政と医師会の協力
・在宅、介護推進事業
・市民を巻き込む地域活動
私は、この講演を聞いて衝撃を受けました。同じ千葉県ながら地域格差があり過ぎます。松戸市の医療介護を追い越そうは思えません。せめて離れずに、ついていこうと思いました。
今年の1月に、安房郡市(3市1町)の医療・介護・福祉連携の会議を開きました。各地区の特色は残し、補う点は助け合い、協力できる所は、更に強固にしようとする会議でした。行政、医師会、多職種が、円卓で討議することが、どれ程大切なことかわかりました。互いの現状を理解し、今後の課題も見えてくるのです。
5月に次回を開き、この会議を発展させ、市民をどのように巻き込んでいくか、討議したいです。
次に、昨年の熊本地震や東日本大震災から、医師会、歯科医師会、看護協会、ケアマネジャ-協会の事務所について、思うことがあります。
・一ヶ所に集まることが良いと思います。
・可能ならば、行政の施設か、保健所のなかにあればと思います。
災害時の行政や保健所からの連絡と、医師会をはじめとする多職種からの報告も大切です。災害医療チ-ムとして活動するには、医療に関する全職種の協力がなければ、不可能だと証明されました。
最後に私的なことですが、昨年の3月に、起震車で地震の経験をしました。当時は、熊本地震の前でしたので、阪神淡路大地震、東日本大震災と同じレベルを、通常の建築家屋、耐震建築家屋、免震建築家屋で経験しました。
耐震建築は横揺れの地震には、ある程度耐えられますが、直下型地震にはどれ程耐えられるか不安です。その点、免震建築は横揺れにも、縦揺れにもかなりの耐久性があります。免震建築ですと、阪神淡路大地震が震度4.5前後、東日本大震災が震度5.5前後に感じました。東日本大震災と同じレベルを通常の建築家屋で体験した時、本当の意味での恐怖を感じました。
そして、これから建築される、行政の中核となる建物と地域の中核医療機関は、可能ならば耐震建築ではなく、免震建築をと思います。
巻頭言 Vol.53 No.1 2017
巻 頭 言
安房医師会 会長 小嶋良宏
本来ならば、新年あけましておめでとうございますという新年の挨拶が適切だと考えます。しかしながらこの原稿を書いていますのはまさしく師走、せわしない毎日を送っており、失礼ながら割愛させていただきます。
今回書きます内容はただ一つ、オール安房医師会。2大行事である医師会総会及び新年会には限りなく多くの会員の出席を目指したいと考えます。
その理由は言うまでもなく会員の参加あっての総会、会員と理事会をつなぐ唯一の場が総会、年に一度顔が見える関係を構築、地域医療にさらに貢献するために会員相互の親睦を深める公式の場が新年会だからです。
数年前よりこの号には3月の総会における事業計画案総論を書いてきました。それはそれで意味のあることかと考えますが、今一度立ち止まり、医師会の重要行事である総会出席者数を見直しますとあまりに少なく、新年度の事業計画案を審議する会としてはあまりにお粗末と言わざるをえません。総論案を書くよりも出席を促す文章を書き、総会を多数の出席者による活発な意見交換の場にしたいと考えます。
理事会は会員に対し限りなく情報公開しているつもりです。時々、理事会はどうなっているのか、何をしているのかという声を聞きます。医師会ニュースに理事会活動、講演会の内容などを書いていますが、情報が100%会員に通じる訳でもなく、また読んでも100%理解できる訳でもありません。ただ読むだけでは理解できない内容もあり説明が必要かと考えます。
総会の場で常日頃思っていること、疑問や批判、医師会ニュースの内容などについて質問、発言していただければ誠意を持って返答、説明致します。
この医師会ニュースが会員のお手元に届く頃には平成29年の新年会は終わっているかもしれません。毎年の新年会の出席数はどうでしょうか?総会と同じく約50名、いつも同じ顔ぶれです。仕事の都合などで欠席されるのはやむを得ません。新年会、総会などに対しある種のアレルギーを持っている会員がいるかもしれません。酒席を強要するつもりは全くありませんが、年にたった一度の仲間の集まりです。ぜひ出席していただき、親睦を深めることが会員相互の理解や病診連携、診診連携の一助となると考えます。
過去形になりますが、平成28年12月から担当理事、幹事あげての新年会出席攻勢を展開いたしました。多数ご参加していただき盛大な新年会にしたいと考えます。
我々は会員あっての安房医師会と言うことを肝に銘じ、2大行事である総会と新年会の出席者を増やし、親睦、結束を固め安房医師会の組織を盤石なものとし、他地区医師会や県医師会に一目置かれるような組織を目指し、地域医療に貢献して行きます。
巻頭言 Vol.52 No.6 2016
巻頭言
安房医師会 副会長 原 徹
毎年9月になると前年度の医療費が厚生労働省から公表されます。それによると2015年度の概算医療費は過去最高の41.5兆円になるとの事、2014年度の医療費は40.0兆でしたので前年度よりさらに1.5兆の増加になりました。その結果として医療費の抑制が一層声高に謳われています。また医療費増加の原因とされる『高齢者や障害のある方への医療を含めた社会保障の在り方』も同時に議論されます。この様な社会情勢の中で去る7月には神奈川県の障害者施設で殺人事件が起きました。さらに9月下旬には横浜の病院でも高齢者に対する殺人事件が発生したことは記憶に新しい事です。これ等の事件は非常に凶悪な事件であることは間違いない事実ですが、異常者による犯罪として簡単に片付けて良いものでしょうか? 医療に関わる我々は人間の健康そして生命を極めて大切なものであるとの信念に基づき、疾病予防や治療に力を尽くしてきました。また社会正義を掲げ弱い立場にある方々を救済すべく努力しています。然し『検査や治療がどこまで適切であるのかを悩む事』も少なくありません。その理由の大きな部分は『地球の資源が限界に近付き、恒常性の維持が危ぶまれている』からでは無いでしょうか? 2016年現在、地球全体でみると総人口は73億人を超え、地球と言う星の至適人口と言われる40億人を遥かに超えた状態になっています。1960年には30億人であった地球人口はこの50年間で2倍以上に急増した事になります。さらに2050年には97億人となり2100年には100億を超えると予測されています。その結果、食料を初めとして殆ど全ての資源が枯渇した状態となります。そして『限りあるものを求めての諍い』が生じることは必至であり、さらに環境破壊による地球温暖化等の影響で『過去に経験のない災害』も頻発しています。そして戦禍や貧困による難民の急増も大きな問題となっています。既に地球人口の調整が必要であることは多くの方々が認識していると思いますが、真摯な議論は為され難く口を閉ざすのが現状であるかと思います。
ところで『ダ・ヴィンチ・コード』や『天使と悪魔』を書いた小説家ダン・ブラウンは2013年に『インフェルノ』と言う小説を出版しました。この作品は映画化され、この10月末に公開予定です。その内容は天才的な生化学者が詩人ダンテの叙事詩「神曲」<地獄篇インフェルノ>に隠した暗号をラングトン教授が解き明かして行く内容です。天才科学者は深刻な地球人口増加問題を『このまま何も対策を講じなければ人類は100年後に滅びてしまう』と捉え、その解決策として、『人口を半数に減らす為のウィルス』を生み出しました。そしてダンテが予言した人類の“地獄”の未来図=<地獄篇インフェルノ>になぞり、人口削減計画を実行に移しました。この中で我々人類に突き付けられた課題は『100年後の人類滅亡』を受け入れるか、それとも『人口を半分に減じることで人類を生き残らせる道』を選ぶのか?と言う極めて深刻な選択です。翻って現在我が国では少子化対策が声高に叫ばれています。出産が増えなければ高齢者を支える若い世代が不足する事は事実ですが、地球規模で考えると矛盾が生じることは否めません。
今年のノーベル医学生理学賞は大隅良典博士が『オートファジー』に関する研究で受賞されました。そしてこの分野は『生命と死』の根幹に関連するものです。ヒトを含む高等生物の個体発生の過程では、一旦分裂によって生じた細胞が自発的に死んでいくことで様々な形態形成が進みます。このときに見られる細胞の死は、その生物が遺伝情報にあらかじめ含んでいる(すなわちプログラムされていた)という意味からプログラム細胞死(Programmed cell death)と呼ばれています。そしてこのプログラムされた細胞死の過程には3型があり1型はアポトーシス、2型はオートファジーを伴う細胞死、3型はネクローシス、に分類されています。アポトーシスは個体をより良い状態に保つために積極的に引き起こされる『管理・調整された細胞の自殺』であり『ダメージを個々の細胞レベルで食い止め、個体の生命を守る』危機管理システムでもあります。この様にアポトーシスは不必要な細胞を除去するシステムとして働き、オートファジーは細胞内の不要なタンパク質を分解し正常な発生に寄与するシステムであると同時に『飢餓時の生存システム』として個体の恒常性維持の為に機能するものです。これ等は感染症や血流障害、物理的破壊・化学的損傷が原因となる『ネクローシスによる死』とは対義的な関係にあります。
この様に個体が飢餓状態におかれるとアミノ酸の供給が断たれ、細胞にとっては生死に関わる重大なダメージになりますが、オートファジーが働くことによって、細胞は一時的にこのダメージを回避することが可能だと考えられています。然しオートファジーによる栄養飢餓の回避はあくまで一時的なものであり、飢餓状態が長く続いた場合には対処することができません。オートファジーが過度に進行することで、細胞が自分自身を『食べ尽くしてしまい、細胞が死に至る』と考えられています。ところでアポトーシスは15億年前に有性生殖と同時に生まれたシステムです。有性生殖は『遺伝子をランダムに組み換えることで子孫を残すシステム』であり、その過程で不適切な遺伝子の組み合わせを除去する目的で生まれたのがアポトーシスです。そこにオートファジーのシステムも加わり人類としての進化・発達が為されて来たと思います。然しその前提としての『礎となる死』があったことは間違いない事です。人類の進化の流れの中で『死の積極的な意味』も捉え直さなければならない時代になったのかも知れません。現在の『社会保証制度』も十分なプログラムを伴わなければ『国を食べ尽くす』結果を招く可能性があるかと思います。人は必ず死を迎えなければなりません。後に残る人や国、そして地球への負担を軽減し、可能であれば『ネクローシスによる死』では無く、次代に役立つ形でそれを迎えることが出来れば幸いかと思います。