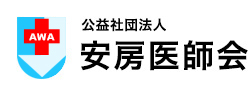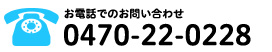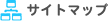巻頭言 Vol.52 No.5 2016
巻頭言
安房医師会 会長 小嶋良宏
梅雨明けの夏真っ盛りの中、仕事を終え10キロほどランニング、エアコンの効いた部屋で、汗をしぼる方が簡単と思いながら無い知恵をしぼってこの巻頭言を書いております。これを読まれる頃は朝夕に涼しい風に乗って鈴虫の歌声を聞くことができることでしょう。
私、齢57歳、諸先輩から見たならば、まだまだひよっこ、丁稚、鼻たれ小僧と言われそうな年齢ですが、高校時代の同級生に会うと言葉のはしはしに定年後はどうしようか?定年延長するかしないのか、転職するかしないかなど、第二の人生の生き方を模索し悩んでいる会話を多く聞き、世間一般で見るとそのような年齢になったのかと改めて認識いたします。
定年の話題はさておき、70歳まで足腰が丈夫でかつ大きな持病もなく元気でいられると仮定すると、春の花見、夏のバーベキュー、秋のキャンプ、冬のスキーなどを経験する回数は多くて10回、同様に一生の間にたった一回しか行くことができない観光地や海外、一回しか会えない人物の存在も考えられます。
この6月から安房医師会理事会は岡田唯男理事を迎え新体制となり、心機一転、理事一丸となりその運営をしていきます。残された任期は2年を切りました。理事会であと何回議論ができるでしょうか。
残りの理事会の回数は40数回、総会はあと4回開催しましたら任期終了となってしまいます。
これからの理事会を大切にし、会員のため、地域医療を守るため、おこがましいですが後を担う理事を育て、悔いのないよう職務を執行いたします。
私には定年が決められている訳では無いですが、引き際が肝心、自分一人でで考え、決定し実行、静かにfade outすることができれば幸いです。
巻頭言 Vol.52 No.4 2016
巻頭言
安房医師会 会長 小嶋良宏
梅雨の時期、まるで夏のような日差しと、言葉通りの梅雨空と目まぐるしく変化している日々ですが、心は梅雨空のように少々暗い日々が続いています。もちろん心明るくなる話題もあります。
会員の方々は最近の千葉県医師会雑誌を読まれ、事の成り行きに多少なりとも疑念を感じているかもしれません。
ここで説明をいたします。
昨年の秋、県医師会より財務委員会の委員を推薦するよう安房医師会あてに依頼が来たため理事会にて審議し、適任と考えた理事を推薦しました。県医師会理事会にて審議した結果、財務委員にふさわしくなく推薦は却下すると返事がきました。ふさわしくない理由が3点ほど記載してありましたが、その理由に納得できかねて今回のような県医師会雑誌のような内容となりました。
県医師会会長会議の席上、その理由の説明と撤回を求める発言をしましたが返事がなく、仕方なく内容証明を県医師会に郵送しました。
3月の臨時総会にても、その説明を求めたところやっと県医師会から返事が届きました。その内容とは、県医師会理事会にて再審議したがやはり財務委員にはふさわしくないと、こちらの要求通りにはなりませんでした。
安房医師会としては、言うべきこと、やるべきことを全て実行した結果ですし、県医師会理事会の決定には従わざるを得ませんが、こちらが100%納得したかといえばそうではありません。この先、県医師会の決定を不服とし、安房医師会があれこれと行動を悪戯に起こし、仲違いを続けてもお互いにいいことは全くもってありません。
会長として、この先どうしたらいいのでしょうか?
今できるであろうことは、県医師会の理事、議長、監事、職員の方々とさらに太いパイプを作り交流、互いの信頼関係を築き、二度とこのようなことが起こらないようにするほかありません。
この先2年を費やし、さすが安房医師会と言われるような体制や交流関係を構築するほかはないと考え、決意を新たに理事一丸となって職務を全う致します。
かねてからの新医師会館の件です。新しく建設すると今まで述べてきましたが、建設という文言の解釈には、建物を新しく建設すると言う解釈と、医師会館という存在を新しく造るという解釈も存在します。存在を新しく造るにはどうしたらいいでしょう?新しく建物を造らないで、どこかの施設に間借りしても医師会館を造ると言うことになります。
確かに財政的には新しく建物を作るには巨額な資産を要しますし、維持管理費もかなりの額になることでしょう。安房医師会の財政を考えるに建物を新たに建設するよりも、行政、その他から建物を間借りした方が資金が少なくて済みます。今後は新しく建設するのかまたは間借りか、この両面で検討していきます。今まさに新会館に関する趣意書を書いている途中です。完成しましたら、会員の方々や行政、関連団体にも配布し説明、5年後をめどに新医師会館に移転したい考えます。
巻頭言 Vol.52 No.3 2016
「 地域医療 」
安房医師会副会長 竹内 信一
今回、地域医療に思いをはせ、考えてみました。
4月からの診療報酬改定、医療圏の問題、人口減少・少子高齢化など今後の地域医療は、崩壊の危機にさらされていると思える今日この頃です。皆さんは知ってか知らずか判りませんが、更にこの問題に負の影響を与えると考えられるのが2017年度から変わる医師の専門医制度です。その内容は、従来の2年間の初期臨床研修に加え、内科や外科といった基本領域からの一つを選び、さらに3年間の研修を受けるということで、この制度変更で特に影響を受けているのは地域医療に必要な内科だと思います。新制度では循環器内科や呼吸器内科などの専門的なトレーニングを始めるのは早くとも30歳、研修を終えるのは30歳半ば以降になり実質的に専門医が減ることになります。総合診療医を増やそうとする国の施策の思うつぼではありますが、浅い知識、技術の医者が増える可能性があると思うのは考えすぎでしょうか。
さらに新制度は地域にも大きな打撃を与える可能性があります。今まで主に大学病院は研究、国公立・民間病院が地域医療を担い、若い医者の多くは後者での研修を希望してきました。ところが新制度では、大学病院などでしか治療していないようなまれな疾患も全員が経験するよう求められています。そのため、民間病院の多くは大学病院と連携することになり、研修を受ける医師は大学病院でも一定期間の勤務を求められるので地域医療への影響は必至と思います。
では今後、地域医療の再生はないのでしょうか?再生の道は、地域医療のパラダイム・シフトを促す「生活を診る」病院、診療所などの創造ではないのでしょうか。従来、急性期医療こそが「医療の主役である」という風潮が強く、「生活を診る」という医療の原点を軽視してきた結果だと思います。従って、この視点からの総合診療医の育成は急務です。さらに、今後は急性期病院と在宅医療の中間に位置して両者をつなぎ、患者さんを生活に戻すため「人を診ること」に集中する医療提供が必要で、その中心となるのが地域包括ケアシステムと思われ医師会もその観点から、積極的に関与することが求められているので私ももうしばらくは医師会活動に携わっていきたいと思っている今日この頃で、一医師のつぶやきです。
巻頭言 Vol.52 No.2 2016
「 安房風 」
安房医師会理事 田中 かつら
安房医師会理事になってまだ日が浅い私が、巻頭言を任せられるのは少し場違いではないかという感は、この医師会ニュースを読まれるどの方も感じていらっしゃるだろう。当の私がそうであるからだ。諸先輩方の文章力に感心し、さて自分は何を表現できるだろうか。思いつくままの散文をご容赦願いたい。
私はこの安房地区(正確には南房総市千倉町)に居住するようになり10年が経った。この地には地縁もなく、生まれ育った東京、目黒より東に住むことは全く考えもしなかった。しかし何か引き寄せられる魅力があったと信じている。それまでいろいろな土地を旅し、その地の文化を知ることが楽しみでもあった。その地の魅力とは何か?旅人が興味を持つのは、その地に長く培われた文化、大切に守られた芸能であり、風習、技術である。その奥深さを知るには、その土地の人々の生活を知らなければならない。今の時代まで引き継ぐことができたというそのことが、今の文化を形作っている。そして、その土地の人々がその文化を「楽しんでいる」ということ。旅人はそれを少し外側から窺うことが楽しみなのである。
どこの地に行っても、旅行客を呼び込もうと、旅行者向けのいわゆる箱物が多い。なぜここにヨーロッパの村があるのか?どうしてここに南国の島なのか?中に入るとやはりどこも同じ土産屋が並ぶ。旅行者に向いた観光は少しの魅力もない。一度行けば十分である。いや、行く意味があるのか?と疑問である。なぜなら、それはあくまでも模倣であり、地の文化を象徴するものではない。もてなしは必要だが、観光客に媚びる文化はすぐ飽きられるのは当然である。「○○風」「南国の○○」は偽物であることを知らなくてはいけない。
私は「移住組」である。安房の文化は学ばなくては知り得ない。この地の文化は私のDNAには組み込まれていない。しかし、よそ者だからこそ、この地の魅力は人一倍感じることができると自負している。こんなに素晴らしい自然と人々が存在しているのに、地の人は「この土地にはいいことがない」「ここでは苦労するだけだ」と話す。これでは、子供や孫がこの土地を離れてしまうのも仕方がないと思う。魅力ある土地であることをどうやってわかってもらえるだろうか?こんなよそ者を実は温かく迎え入れてくれる心優しい人々がいて、自然からの恵みを豊かに受けられ、時に厳しい自然にさらされる環境で、互助が当たり前にある土地である。新しいことは必要ない、今の魅力に皆が気付くことで、この地の大きな力になると感じている。
地域包括ケアシステム構築をと叫ばれ、三市一町はそれぞれどうやって形あるものにするのか、現在進行中である。安房医師会もその構築にどうかかわるべきか?まだ手探りの状態である。私のような移住組から見ると、この安房ではもうすでにこのシステムはできているのではないか?と感じる。行政や医療や介護や福祉の方々とはとても近い存在で、何かあるといつでも話ができる関係がすでに存在している。それを目に見える形にするだけである。何か足りないとすれば、縦割りの行政単位を超えること。これを横につなぐことができるのは、安房医師会の役割ではないかと考える。システムの一部でもある医療は、安房地域全体を考えないと成り立たないからである。全国各地でこのシステム作りでは、いろいろな取り組みがなされているが、それぞれに特徴がある。しかし、それを真似ることはできない。その土地に培われた文化があるから、同じシステムはない。そこで「安房風」システム構築が必要なのである。この土地で暮らす誰もが、同じ地で安心して暮らせるために、困ったら、みんなで解決できる場を作る。ここで生まれ育った人がいて、その人を知る周りの人々がいるからこそ、一緒に考えることができる。それが自然にできる地のつながりが、ここにはすでに存在している。都会のようなところではきっと考えられないことだ。
なにか象徴的な形が必要とあれば、こんな一案もある。新医師会館建設をこの地域包括ケアシステムと関連づけて考えられないかと思っている。会館建設の是非については、まだ会員の承認を待つ段階であるが、単なる医師会館という単独のものではなく、行政、歯科医師会や薬剤師会、ケアマネジャー連絡会など多職種が一同に介する場があれば、ここに来れば誰かがなにか知恵を出せるという「安房風合同庁舎」ができないだろうか?ワンストップで問題解決ができるのではないか?ハードの問題で全て解決できるわけではないが、すでによい連携がある安房地区だからこそ考えられることでもある。どこかの真似ではなく、「安房風」という独自の発想で、この土地の良さを多くの人とともに楽しみたい。
巻頭言 Vol.52 No.1 2016
年頭所感
安房医師会長 小嶋良宏
2016年もつつがなく明け、新年の抱負や期待に胸を膨らませ、楽しい計画に心躍らせ正月を過ごされたことでしょうが、いつの間にか松飾りはその役目を終え、普段通りの生活がもどってきた頃かと思います。
お屠蘇気分はさっそく引退させ、本題に入ります。
数年前より、3月の総会の事業計画案総論をこの新年号に書くこととしてきました。今回は2項目、どちらも過去に巻頭言に書いた事があり、児童、生徒の健康に関する内容です。
ここ数十年間、耳鼻咽喉科、眼科の新規開業は全くなく、その開業医数は10名を切っています。この少人数で3市1町の幼稚園、小中学校、高校の健康診断をしているのが実状です。医師会会員にも高齢化の波が押し寄せてきており、最近、ご高齢の会員の方が校医を辞退され、新たに公募しました。
今後、耳鼻咽喉科、眼科の校医が不足する懸念が多大にあります。
教育委員会にもこの医師会ニュースは届けてあることより、委員の方々の頭の片隅には将来の校医不足の認識はあるかと思います。この解決方法を考えるに、まずは市町の境界を超え専門医が協力する必要があります。
また、近隣の大病院の院長、各科医師にお願いし、新たに校医になっていただく方法や、ちば県民保険予防財団に委託するという方法もあります。
本年度はこの懸念を各機関と議論し、解決方法を考えていきます。
数年前、某会員から学校保健について意見がありました。健康診断を実施せず、父兄や児童、生徒へ眼科領域の内容、例えば視力維持の意味、衛生、外傷時の対応、疾病のことなどを教育、啓蒙、また養護教諭対象には視力測定などの研修をしたらどうかという提案でした。法律で決められている健康診断は実施しないわけにはいきません。その後理事会で審議し、眼科領域だけにとらわれず、この提案を広い意味としての健康教育と捉え、教育委員会と会合を持ちましたが未だかつて実行されていません。
この提案を実行するためには幾多の問題を解決しなければなりません。
私見を下記に列挙します。
1、教育、啓蒙の内容であるが内科、整形外科、耳鼻科、産婦人科、その他の領域まで広げるのか否か。
2、講師をどうするのか?
3、3市1町の教育委員会と協議をするのかどうか?特定の教育委員会とだけ協議するのか否か?
4、同じく3市1町の全小学校、全中学校を対象とするのか否か?特定の学校を対象とするのか否か?
5、対象学年はどうするのか?
6、単年度とするのか?継続するのか否か?
その他、市民公開医学講座のように大きな会場で安房地域の児童、生徒、父兄、教諭を集めて実施するという方法も考えられます。再度理事会で審議し、問題を再考、論点を整理し、教育委員会と会合、実施に向け協議していきます。
残された任期は6ヶ月となりました。理事一丸となって将来を見据えた医師会運営を実施していきます。
巻頭言 Vol.51 No.6 2015
希望と諦め、できれば never ending
安房医師会副会長 原 徹
NHKの朝ドラ『まれ』が9月で終わりました。『地道にコツコツ』進む人生とリスクを負って『大きな夢を追う』人生はどちらが良いのか? 朝のドラマなので“明るく前向きに”と言う内容、即ち『地道』も『夢』を追うのもどちらもpositiveな姿勢であり、また能登の地域での住民の連携、地域社会の在り方など同じ“半島の先”に住む者としては参考になるので毎回楽しみにしていました。今回は“まれ”の父親の名前が“徹”であり、自分でも毎日叱咤激励されている様な気分でしたが、最後まで父親としての在り様が見えない結末、また何とか現在社会のnegativeな閉塞感を払拭できないか?との淡い期待に対しては若干不満が残ってしまいました。翻って安房の地域を見ると夢を掲げ、新たに事業創設している事例は稀で、一方地道にコツコツも儘ならず、規模の縮小や廃業を余儀なくされている方が多いのが実状かと思います。それでも“元治”さんのつくる塩の様に理解され、評価されれば立派な仕事として継続できる!! そう思って頑張って仕事を続けている方も沢山居られます。ところが一方では夢が叶わず『閉塞感に苛まれ虚無の世界に引きずり込まれている』方々や、『初めから夢を持てない』若者が増えているのも現実です。
思い返すと1970年の日本レコード大賞・歌唱賞は、岸洋子さんの歌った『希望』でした。
その歌詞をおさらいすると
「希望という名の あなたをたずねて 遠い国へと また汽車にのる
あなたは昔の あたしの思い出 ふるさとの夢 はじめての恋
けれどあたしが大人になった日に 黙ってどこかへ 立ち去ったあなた
いつかあなたに また逢うまでは あたしの旅は 終わりのない旅」
大人になると夢が黙って何処かへ行ってしまう。それでも諦めずに人生と言う旅を続ける。貪欲と批判されても夢や希望を捨てない。そんな気持ちが込められた歌であると思います。この“意地を張っている、プライドが高い”と言われても諦めずに前に進む人間の性が高度成長期の我が国には色濃くあったと思います。そして当時は社会の問題を考えようとするとき、その前提として明確な希望・目標があったかと思います。希望は欲望や目的でもあり、その達成に向かって社会生活での消費・学業・就業そして家族の協力などが行なわれていた時代でした。しかしその前提自体が揺らいでいます。『失われた10年』と呼ばれた時代もとうに過ぎたのに、今でも『社会を覆う閉塞感』を打破することができていません。そしてこの閉塞感の根源には『希望の喪失』という深い闇が潜んでいる事に、多くの方が気付いています。
進歩、発展、成長、そんな言葉を信じられる時代には個々が何を欲し、何を目的として生きているのか、そして社会がどこに向かっているのかの具体的な希望が見えていました。しかし現在ではそのような想定が失われつつあるのです。
Die unendliche Geschichte、ドイツの児童文学作家のミヒャエル・エンデ(Michael Ende )の書いた物語はネバーエンディング・ストーリーとして84年に映画化され、ご覧になった方も多いと思います。虚無(The nothing)により不思議な異世界「ファンタージェン」は崩壊の危機に瀕しました。これを救うのは『希望を持つ勇気』ではなかったでしょうか? そして虚無の世界は今日も確実に拡大しています。若者には大いに夢と希望を持って欲しいと思います。そして大人も夢と希望を忘れずにと願っています。但し年を経るごとに出来れば私的な夢から公的な夢に、徐々にシフトして欲しいと個人的には願っています。
終わりに“希望”の歌詞、2番と3番を載せ、私の果てしの無い夢は続きます。
「希望という名の あなたをたずねて 今日もあてなく また汽車にのる
あれからあたしは ただ一人きり 明日はどんな町につくやら
あなたのうわさも 時折り聞くけど 見知らぬ誰かに すれちがうだけ
いつもあなたの 名を呼びながら あたしの旅は 返事のない旅」
「希望という名の あなたをたずねて 寒い夜更けに また汽車にのる
悲しみだけが あたしの道連れ となりの席に あなたがいれば
涙ぐむとき そのとき聞こえる 希望という名の あなたのあの唄
そうよあなたに また逢うために あたしの旅は いままた始まる」
(『希望』作詞:藤田俊雄 作曲:いずみたく)
巻頭言 Vol.51 No.5 2015
真夏の夜の夢
安房医師会長 小嶋良宏
その日は2020年秋、東京オリンピックは成功裏に終わり、日本のみならず、世界中の人々がメダル獲得数に酔いしれている台風上陸前の1日。その興奮冷めやらない人々とはまるで正反対、胃潰瘍悪化一歩手前の7名のつらい火曜日。朝から豪雨と強風が吹き荒れる夕刻6時、千葉県安房医師会理事会開催が危ぶまれたが、交通機関には支障は無く定刻通り開催された。
出席理事の総数は7名。毎年会員数は減少、理事の引き受け手も少なく、その都度定款細則を改定し、今や理事定数は以前の半数程度となってしまった。皆の表情は暗く、覇気も無く、あきらめの境地の見本市のようであった。総務担当理事が事務的に開催の口火を切り、会長挨拶、報告事項と重苦しい雰囲気の中、議事は進行された。その日、会長専権事項である審議事項は3項目と少なかったが、安房医師会の将来を決める重要な案件であった。
1項目目、南房総市教育委員会から、来年度の児童、生徒の健康診断をするために、医師会より耳鼻科医、眼科医師の推薦をして欲しいとの要望であった。少子高齢化に伴い、児童数、生徒数は激減、その結果、統廃合が進み、学校数が減少したため、例年ならば耳鼻科医、眼科医の必要最低限の医師は確保できていたのであるが、高齢化は開業医にも襲いかかっていた。市内の医師の高齢化が進み学校医辞退の申し出が多数、また新規開業の医師はゼロであった。数年前より、教育委員会に将来医師を確保できなくなる可能性があるので、準備をするよう進言してきたが、まさか本当にゼロになると考えておらず、その対策もゼロであった。いつもなら活発な討論がなされるはずであったが、推薦できる医師がいないため、教育委員会にはその推薦は不可能であり、館山市、鴨川市の医師の手を借りる他に方法はないと決議された。しかしながらどの市も医師数は激減していることは言うまでもない。
2番目の審議事項は来年度の予算編成案についてであった。例年ならば、1月の理事会にて審議するのであるが、予算編成不可能と税理士から報告があったため早めの審議となった。ここ数年、会費収入は極端に減り、医師会の維持、運営は数年前より綱渡り状態であったが、なんとか資産をやりくりし低空飛行でもちこたえていたが、収入と支出のバランスはまるでTotenkreuzのごとくであった。協力金や補助金の増額の要望を再三再四申し出ていたが色よい返事は得られなかった。銀行融資を考えてみたが、返済する原資も無く、たとえ今年融資実行されても、来年には借金を返すために新たな借金をすることになるであろうことは火を見るより明らかであった。八方塞がりとは良く言ったものである。審議することも無く執行部一任となった。
最後は安房医師会の解散および他医師会と合併をするのかどうかの審議であった。
会員数激減に伴う収入の減少が続けばいずれ医師会運営は不可能になる事を予想、数年前より事あるごとに顧問会に相談、総会の度に会員に説明、将来他医師会と合併する事になるかもしれないと唱えてきたが、とうとう理事会で最終決断することとなった。
安房医師会という名称を残したい気持ちはあるが、審議事項2が上程された今、破綻する前に他医師会と合併する他に選択肢はないのであろうか?どの理事からも意見は無く、いたずらに時間ばかり経過、会長一任と決議され、臨時総会を一月後に開催予定と口頭で締めくくり、理事会を終了。
外は嵐の前の静けさであろうか、雨風は弱まってきたと感じた頃、朝のアラームが鳴り、真夏の夜の夢から覚めた。
巻頭言 Vol.51 No.4 2015
安房地域医療センターの今後
安房医師会理事 西野 洋
安房医師会病院が社会福祉法人太陽会に移譲され、安房地域医療センターとして再出発したのが7年前で、私が亀田総合病院から安房地域医療センターへ赴任して早くも5年が経過しました。この間、亀田信介理事長、水谷正彦院長を中心として職員一同努力してきました。地域のニーズに応えて、質の高い医療・福祉サービスを充分量提供するために、救急センターの増築、臨床研修病院の認定、ISO9001の認証、日本病院機能評価の認定、中核地域支援センターの配置や無料低額診療の開始、安房医療福祉専門学校の開学などを行ってきました。最近では、フローレンスガーデンハイツという独居老人向け高齢者住宅の取り組みも始めました。
今後、太陽会が館山南房総地区において、安房地域医療センターを中心として、どのような事業展開を進めるべきか、いろいろとbrain stormingを行う機会がありました。そこで出た様々な意見は大きく4つの柱(W・E・E・P)に集約されました。
「W」はWelfare=社会福祉です。総合相談センターと中核地域支援センターが窓口となり、無料低額診療、フローレンスガーデンハイツなど、経済的・社会的に困難な方々への医療・介護・福祉面での支援を積極的に行ってゆきます。「E」はEmergency=救急医療です。今後も24時間365日の救急医療や急性期入院診療のさらなる拡充を目指し、地域の大規模災害への準備をしつつ、病院の理念である「明るい笑顔で最適な医療を提供する」べく努力をいたします。もう一つの「E」はEducation=教育です。地域医療の現場で地域医療を担う医師を育む地域ジェネラリストプログラムという初期研修プログラムと、地域ホスピタリストプログラムという後期研修プログラムを継続・発展させてゆきます。また看護師の卒前・卒後教育を推進してゆきます。今後も、地域の医療・介護・福祉を担う人材育成に力を注ぎます。そして、最後の「P」はPrevention & Promotion=疾病予防と健康増進です。従来行ってきた住民検診に加えて、今後は健康増進にも力を注ぎます。すでに職員有志がボランティアで日曜日を利用して一般市民向けに健康増進を図るAWAカフェプロジェクトが始まっています。今後はP & Pをさらに充実させてゆきます。
これら4つの頭文字「WEEP」は、英語で「涙する」という意味です。社会福祉法人太陽会では、医療・福祉・介護・教育事業部門が連携をとりながら、身体的、精神的、経済的、社会的に涙する人びとに寄り添う活動を展開してゆきたいものだと願っています。このような活動は、太陽会単独でなし得るものではありません。安房医師会の先生方との連携を密にしながら、行政や地域住民と対話しながら進めてゆきたいと考えています。
巻頭言 Vol.51 No.3 2015
『巻頭言』
学校保健担当理事 林 宗寛
道ゆけば路地の角、あるいは屋根瓦の上などに、散った桜の花びらが残っているのを目にします。何となく人生のはかなさを感じる反面、美しい国、日本に生まれてよかったなと思う今日この頃です。
思えば二年前の六月、二度目の安房医師会理事を拝命いたし今日に至っております。他の皆様に遅れを取るまいと、ひたすら暗中模索の状態でやってまいりましたが、ふと気づくともうじき任期満了です。今思うと、あっという間だった感があります。不束にして至らぬ点も多く、会員の皆様にはご迷惑をおかけした事を申し訳なく思っておりますが、あとしばらく頑張りますのでご容赦願います。
自分は学校保健担当理事です。学童の保健、健康に対する行政との関わりや折衝は苦労もあるものの、医師とは違った立場の方々とのふれ合いを通じて新しい観点の発見や驚きなど、興味深いものも多々ありました。中でも印象深いのは小児メタボリックシンドローム健診指針の再検討の仕事でした。小児メタボリックシンドローム健診に関しては、現在のところエビデンスのしっかりしたガイドラインが確立しておらず、かなり古い判断基準での健診が行われておりました。そこで、実情にマッチした基準を策定すべく、小児科医を中心としたチームを作り、会議を重ねて新基準を作成いたしました。昨年、安房郡市四行政と擦り合わせを行い、来年度からの実施を念頭に検討中です。実情に即した施行可能なものができたのではないかと思っておりますが、後任の理事にしっかりと引き継いでいきます。
安房医師会の現在の明るい、前進すべき話題としては新医師会館の創設(可能か? または間借り?)、およびホームページのリニューアルがあげられます。両者とも実行グループを立ち上げ、前向きの姿勢で検討中です。ホームページに関しては具体的かつ着々と進捗しております。新医師会館については未だに「?」の状態ですが、鋭意進行中です。
我が医師会も永い歴史を誇り、地域住民のためにも今後ますますの発展が望まれます。理事を退いた後にも、我が医師会を愛する気持ちは変わらず持ち続けます。今後とも皆で頑張っていきましょう。
巻頭言 Vol.51 No.2 2015 予防接種における医療事故防止に向けて
地域医療・災害救急医療担当理事 野崎 益司
誠に残念なことであるが、医療機関におけるワクチンの誤接種(予防接種実施規則に反する事例)が後を絶たない。安房医師会では昨年、接種事故防止対策の一環としてワクチン接種に関するリスクマネージメントに詳しい専門家を招聘し、医師、看護師および医療事務員を対象に講習会を開催するとともに、すべての会員へ講習会で使用した事故防止ろうかという疑問を抱くのは至極当然のことである。現在我が国では異なる2種のワクチンを同時以外に接種する場合、初回が
不活化ワクチンなら6日以上、また生ワクチンの場合には27 日の間隔をあけて次のワクチンを接種することが義務付けられている。この日数設定の根拠は、副反応の出現時期が不活化の場合は1週間以内に、また注射生ワクチンの場合は接種後4週間までに出現しやすいので、その間は他のワクチン接種を控えた方がいいだろうという考え方に基づいている。しかし副反応らしき症状が発現している子供に対し、何のためらいもなく次のワクチンを接種する医者が果たして存在するだろうか。またその期間内に異種ワクチンを接種し、もしも何らかの副反応が生じた場合、どちらのワクチンが原因となっているのか判らなくなるというのも根拠の一つとなっているらしいが、この理屈からすると混合ワクチンや異種ワクチンの同時接種など到底あり得ないということになってしまう。とくに現行の同時接種は厳密には接種間隔が最も短い異種ワクチンの接種であることから、それを認可するためには異種ワクチン接種間隔の規定解除が前提でなければ全く理にそぐわないことになってしまう。 このような現状を鑑み、日本小児科学会は平成24 年9月付けで当時の厚労大臣であった小宮山洋子氏に対し、異なるワクチンの接種間隔変更に関する要望書を提出している。その中で同学会は、注射生ワクチン接種後、次の注射生ワクチン接種までの間隔は従来通りの27 日とする一方で、その他の接種間隔には制限を与えるべきでないと主張している。参考までに、米国においては疾病予防対策センター(CDC)の接種間隔規定を採用しており、これによると同一のワクチン接種または注射生ワクチン同士の接種以外においては接種間隔を制限する必要はないとしている。英国をはじめ、すでに多くの国でこのCDC の規定が採用されており、これが現在の世界基準になっていると考えるべきであろう。
予防接種の効果と安全性を確保するために実施規則の設定が必須であることは言うに及ばない。しかし異種ワクチンの接種間隔に関する規則は単に接種スケジュールを複雑にしているだけであり、多忙な外来業務の中ではそれが医療側に負担(ストレス)になっていることは間違いない。また異種ワクチンの同時接種を勧める際、この規則の存在下で安全性を説明するのは事実上不可能である。一方子供たちの側においても、接種日がインフルエンザの流行期に重なるなど、定期または任意接種を受ける機会を失っている子供の数は決して少なくないはずである。いずれにしても、この規則に関しては負の側面しか見えてこないというのが多くの医師の感ずるところであろう。
最後に、現時点におけるワクチン接種は現行の予防接種実施法に従って粛々と履行すべきものであり、たとえ無意味だと判っていても確信犯張りにこの規則に反する行為は厳に慎むべきである。その上で、医師会という組織を通じ、国に対して予防接種実施規則の見直しを要望することが肝要であり、結果的にはそれが真の接種事故に対する最も有効な防止手段となり得るのではないだろうか。