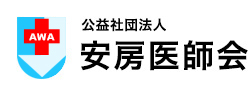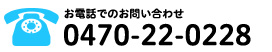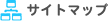巻頭言 Vol.59 No.3 2023
巻頭言
安房医師会 専務理事 小林 剛
新型コロナウイルスによる感染症も第8波を抜け一段落といったところですが、4月初旬の段階では下がり止まりが見られ、むしろやや新規感染の増加が見られております。安房地域での感染者は極めて少ないものの、人口密集地に行って感染して帰ってくる患者も散見され、まだまだ予断を許さない状況です。
3月の厚生労働省の発表では新型コロナウイルスに対するN抗体(ウイルス遺伝子を包み込むヌクレオカプシド蛋白に対する抗体。感染した人にしか出現しない)保有率が人口の42.3%でした。この数字の算出は日本赤十字社で献血した16~69歳、13121名を対象とした調査によるもので、全人口を代弁するものではありません。またN抗体は時間と共に陰性になるため少なく見積もられている可能性もありますが、仮にもっと多かったとしても抗体保有率は50%に満たないくらいでしょうか。本年3月のイギリスにおけるN抗体保有率86%に比べると大きな開きがあります。イギリスのN抗体保有率が4割であった2022年2月頃から小規模な流行は繰り返されて8割強の抗体保有率に至った経緯を参考にするならば、マスク着用が自己判断になった影響も含め、今後小規模な流行が繰り返される可能性は十分あると考えられます。XBBなどの変異株の動向によっては予想不可能な感染状況に至るかもしれません。
5月4日より新型コロナウイルス感染症が5類に移行されますが、依然として様々な問題が残っています。外来受診一つとっても、千葉県保険医協会のアンケートでは新型コロナウイルス感染症への外来対応を行っていなかった医療機関の63%は5類移行後も「診療は出来ない」と回答しています。最も多い理由は「動線が確保できない」でした。入院に関しても重点医療機関における病床確保料は補助上限額を半額に減額の上9月末までの期限が設けられており、10月以降の補助は未定です。またコロナに今まで対応していなかった一般病院における感染患者の入院も、感染対策によるスタッフへの負担や助成金のない経営を考えると簡単に受け入れるということは困難ではないでしょうか。
加えて5月からワクチンの定期接種が開始されますが、先日WHOは60歳未満の健康な成人や基礎疾患のある若年者を中リスクとし、「追加接種は1回までを推奨、それ以上の接種は推奨しない」と方針を変更しました。定期接種の希望者がどれだけいるか予測が困難な状態となっています。スタッフへの対応も悩みどころで、WHOは医療従事者を高リスクとして「半年から1年の定期接種を推奨」としておりますが、今年の1~2月に最終接種をしている医療従事者は春の定期接種を受けなくてもいいのではないかとも思います。
いずれにしても、様々な不安や疑問を残しつつ新型コロナウイルスに対する対応を「非常時」から「常時」に変換するタイミングがやってきたことに間違いありません。マスクを強要されてきた思春期の若者には、マスクをとったらがっかりするという「マスク詐欺」なる言葉も生まれ、マスクを外しにくいと感じる若者もいるようです。よもや新型コロナウイルスパンデミック前の世界に戻ることはありません。これからどのような生活様式が定着していくのか、興味深く見守っていきたいと思います。
巻頭言 Vol.59 No.2 2023
巻 頭 言
-我が医者人生を振り返ってみて-
安房医師会 副会長 竹内信一
安房地域も3年余、新型コロナ禍に悩まされてきましたが、ようやく終息の兆しが見え始め、平穏な日々を送れる今日この頃となりました。しかし、コロナウイルスは変異を繰り返すため消えることはなく、今後も油断は禁物です。私も昨年12月に新型コロナに感染、結膜炎・咽頭違和感・嗅覚障害と1ヶ月近く後遺症に悩まされました。この時に、古希を越えた今、今後の終活をどうするかが頭をよぎりました。当然、現役リタイアは前提ですが!そんな時、私の医者人生はどうなっていたのだろうかという想いに至り、一筆したためようと思います。
私は東京医科歯科大学医学部(今度、東京工業大学と合併するため東京科学大学に…淋しい)卒業後、泌尿器科に入局、その後、関連病院や関連大学を2~3年毎にローテーションして泌尿器科の研鑽を積んできました。その間には良き上司も反面教師もいたと思います。その後2002年、縁あって館山病院に入職することになりました。入職後は今迄とは違った地域医療や地域の方々との関係に携わり、当初は戸惑うことばかりでした。そして館山病院入職5年目には安房医師会理事となり、益々ドップリと地域医療に関係することとなり現在に至っています。
一方、館山病院はというと入職10年目に院長に就任、その後は法人の変更などありましたが、昨年6月1日に現在地にリゾートホスピタルにふさわしい新病院が完成、ハード面ではフルスペックの状態となり、今後は医師を含めた人財といったソフト面での充実が急がれるところとなっています。やや館山病院のことを述べすぎたきらいはありますが?
一方、医師会も今後は若い理事の登用が必要で、そのためには教育が十分でなくてはならず、最後に山本五十六の教育4段階法を紹介して締めの言葉とさせていただきます。
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」
巻頭言 Vol.59 No.1 2023
巻 頭 言
令和五年に願いをこめて
安房医師会 会長 原 徹
新たな年を迎え、公益法人・安房医師会を代表して皆様に新春の御挨拶をさせていただきます。
昨年は新型コロナ禍だけでなく、近隣諸国との緊張関係、さらにはウクライナでの戦争も加わり、地域住民の健康管理も含んだ安全保障の在り方を強く考えさせられました。そして実生活では疾病や戦禍による経済の混乱も加わり、インフレが続きました。逆に明るい話題としては年末のサッカーワールドカップが挙げられます。11月23日の初戦は強敵であるドイツと対戦、2対1での勝利を勝ち取りました。11月27開催の第2戦はコスタリカに敗れましたが、12月2日の早朝4時から始まった第3戦では無敵艦隊スペインに対しての逆転大勝利!!沢山の元気を貰いました。
個人的な話で恐縮ですが、昭和60(1985)年に大学医局から臨床研修と同時に医療機械の治験作業を指示され、西独Stuttgartのカタリーネン病院に赴任、衝撃波による尿路結石破砕機の臨床試験を行いました。そんな訳で一時ドイツに暮らしていましたが、当時は現地のサッカー(ドイツ語ではフスバル Fußbar)クラブ・VfBシュツットガルト(現在は遠藤航が所属)が1983-84シーズンでリーグ優勝したこともあり人気沸騰、現地の方々に「お前はサッカーが好きか?」と何度も聞かれました。当時は未だ東西にドイツが分かれており、シュツットガルトにもNATO+米軍基地があった時代です。一緒に働いていた同僚達も、お互いが必ず何処の出身かを問い、その資質・気性まで色付けしていたのを憶えています。
この様に大陸では「何処の生まれであるか?」が重要であり、評価の基軸となります。その様な背景を持つ西ドイツでは1963年に各都市に拠点を持つBUNDESLIGA(ブンデスリーガ)が創立されました。当然の結果として自分の故郷・地域を誇りとし応援する気持ちはさらに高まり、極めて強いものになりました。そして現在では旧西独10州、旧東独5州にベルリン州を加えた計16州からなるドイツ連保共和国には、18のクラブチームが凌ぎを削っています。また各クラブには1部リーグ2部リーグ、さらには3部リーグや4部リーグもありますが、大事な規約として「登録選手中、12人がドイツ人であること。また6名の登録選手が地元で育てられた人でなければならない事」等の制限を設け「郷土愛を基盤とした地元のチームであること」を堅持しています。
日本サッカー協会が1991年にプロリーグとして“Jリーグ”を創設した際にも、ドイツのブンデスリーガを基本モデルとしたとの事です。そして今回は、SAMURAI BLUEを旗印にした日本代表チームにもサポーターが急増しました。館山でも通学する中学生達が対スペイン戦で勝利した朝に「ブラボー」と叫びながら自転車に乗って通学している光景を観ることが出来ました。そして12月6日の深夜も家々の灯りが消えない状態でしたが、その日の決勝リーグ第1戦(対クロアチア戦)は延長戦となり、さらにはPK戦まで戦いましたが、8強入りは叶いませんでした。
ところで、我々がサッカーで興奮している間もウクライナでは砲撃だけでなく大規模な停電、断水やエネルギー供給源の破壊により暖房が利用できないなどの大混乱が生じているのも現実です。
地球上には既に80億人を超える人々が生活を営み、食料や水をはじめ様々な資源の枯渇が生じ、また環境の悪化も進んでいます。そしてこれを解決するには「人口を減らすしか無い」との極論も聞こえてきます。そして現実に繰り返し発射されるミサイル、また我が国の領海侵犯を繰り返す行為などは、どう考えても「挑発し喧嘩を売っている行為」として感じられます。我々が興奮し、平静心を乱すことを意図している行為であると思います。そしてその理由は、「祖国や郷土への愛、誇り」では無く「現状の体制では食べられない・生きて行けない人々が多数存在すること」、そこから「平衡状態を崩し、新たな体制を構築すること」であると考えています。
台湾有事は日本有事であると言われており、台湾での武力衝突が我が国にとっても戦争への入り口になる可能性が極めて高いのが現状です。このため令和5年は、危機管理と安全保障のあり方が最重要課題になる事を覚悟しています。私の願いは「誇りや正義・愛も無い争い」を回避することです。大義のある戦争など殆ど皆無であり、「戦争をするための大義」を掲げ、「最後に残るのは勝者の独善」である事は歴史を振り返れば明らかです。「ミサイルや爆弾よりボールでの戦い」この強い希望を掲げ、令和5年を生きて行きたいと思います。
翻って安房医師会に関しても、その運営に関して様々な問題が現在も継続して存在しています。この間、行政はじめ様々な組織とも連携し、やっと一縷の望み・光が視える状況となりました。安房医師会としての誇りを保ち、共通の敵である疾病や生活環境の悪化を治し、「次代を担う子供や若者たちが愛着を持ち、誇りに出来る安房を再建すること」。「千葉県内の何処にも負けない郷土として安房地域」を構築することが重要な目標であると考えています。我々は安房地域の為に活動しています。このことが皆様に評価していただければ幸いです。
巻頭言 Vol.58 No.6 2022
巻 頭 言
時の流れに思う
安房医師会 副会長 石井義縁
令和4年9月8日に英国のエリザベス女王がスコットランドのバルモラル城で逝去された。ここは、亡き夫のフィリップ殿下からプロポーズされた場所と聞く。そして、11日にエディンバラのホリールード宮殿へ向けてご遺体が運び出された。エディンバラはスコットランドの中心都市であり、ここに壮大なエディンバラ城がある。この城は、「ふたりの女王メアリーとエリザベス」という題名で映画化された、イングランドの女王エリザベス1世(在位1558―1603)と王位継承権を争い、断頭台に散ったスコットランド女王メアリー・スチュアートが、のちにスコットランドとイングランド両国の初の統一王となるジェイムズ1世(スコットランドではジェイムズ6世)を生んだ城でもある。よって逝去されたエリザベス2世女王もスコットランドの血が受け継がれていることになる。先だったフィリップ殿下ものちに、3代目のエディンバラ公爵となった。歴史的にイングランドが制圧したスコットランドでエリザベス女王が最期を迎えたのは、今後のチャールズ3世国王の統治を案じての、国王としての意図した最後の御奉公だったのかもしれない。
外国人に出身は?聞くと、国の名前で答えられることがほとんどだが、イギリス人からはBritishとかEnglishと返ってこない。イングランドとかUK、スコットランド・・・などと返ってくる。サッカーのワールドカップがそうであるように、イギリス代表というチームはない。イングランド、スコットランド、ウェールズ、ノーザンアイルランドの4チームが代表である。これが、GB(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)の構成国である。小生も約20年前に、イングランドより陸路でスコットランドを訪れたことがあるが、国境(ボーダー)を越えるとスコットランド国旗が沢山なびいていた記憶がある。GBからの独立を願っているのか、スコットランドはスコットランドであるというアピールであるのか。争いを経て国を併合したのち、時を超えて併合された国を思い容認する紳士的な対応は、大英帝国のなせる振る舞いであろう。50か国以上のイギリス連邦の首長であるエリザベス女王の葬儀は、無論国葬であったが、世界葬といっても過言ではなかった。映像でしか拝見できなかったが、まるで中世を幻想させる壮大なものだった。
さて、世代交代はどこにでも必ず起こる。安房医師会でも、令和4年6月の理事選にて若干の理事交代があり、小生は副会長を仰せつかった。原会長と竹内副会長の存在が大きく、小生は実感もなく会員にも認められていないであろう。理事になってから常に会員の利益はもちろんのこと、会員の公平性を保つことを基本に考え、それから約10年経った。現在、医師会は財政問題も含め、様々な問題が山積している。今後は、多少なりとも問題を整理し、次の世代交代に向けての橋渡しができればと思っている。
最後に、国葬といえば、安倍晋三元総理の国葬が、9月27日に執り行われた。国葬に賛否があったが、個人的には、国葬に賛成の立場である。
巻頭言 Vol.58 No.5 2022
巻 頭 言
医師会活動の継続を期して
安房医師会 会長 原 徹
7月8日 安倍晋三・元首相が凶弾により、67年間の生涯を突然閉じられました。歴代最年少である52歳で首相に就任。「美しい国」を国家像として掲げ、「戦後レジームからの脱却」をその基本方針とし、多くの国民の支持を受け第1次・安倍政権が発足しました。然し御自身の体調悪化により「意志を貫くための基礎体力に限界を感じた」と53歳で一旦首相の座を降りられました。彼の持病は17歳時に発症した潰瘍性大腸炎であるとの事、その後も常にこの疾病と闘われ、治療を続けておられました。幸い病は程なく軽快され、彼の再任を求める声を受け2012年12月には第2次・安倍内閣が発足。その政治姿勢は一貫して国の安寧・発展を願い、基盤としての「安全保障と社会保障のあり方」を問い、その再構築を目指すものでした。翻って安房医師会はその定款に「この法人は、医道の昂揚・医学医術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、千葉県民の保健と福祉を増進し、もって地域社会の健全なる発展に寄与することを目的とする」と謳っています。
昨今の自然災害、また新型コロナを始めとする種々の感染症の猛威に晒され、安房地域の安全保障も脅かされてきました。そして地域社会の基盤維持の為に「医療・介護・福祉の機能障害・崩壊を防ぐこと」このためには日常的な危機管理が非常に大切である事を痛感させられています。そして医師会組織がその基盤維持に大きな責任を担う機関である事を再認識いたしました。
ところで私事になりますが、会長としての任期は令和6(2024)年6月の定時総会で終了します。平成14(2002)年、今から20年前に齢50で安房医師会の理事に加わり、2006年からは県医師会理事と安房医師会副会長を兼務、2012年からは県医師会副会長・日本医師会代議員となりました。その後も紆余曲折を経て2018年6月から現在の安房医師会長に選任して頂いた私の医師会の活動歴も残り2年足らずとなりました。
この任期中に次の世代へ会務を引き継ぎ、安房医師会に受け継がれてきた医療等のあり方、即ち医道を伝え、さらには組織の財務基盤を整え医師会活動が持続可能になることを目指します。そして近い将来、我が安房医師会から日本医師会へ常任理事を送り出すことを目標にしています。幸い多くの方々の御支援、御理解でこれまで責務を継続することが出来ました。
現役会長としての最後の2年間を精一杯勤めて行く所存です。また我儘なお願いですが持続可能な組織を継続するために従前にも増して御協力をお願い申し上げます。終わりにこれまで医師会組織を支えて下さった皆様に心からの感謝と御礼を申し上げます。
巻頭言 Vol.58 No.4 2022
巻 頭 言
安房医師会 理事 相正人
理事会に入り二年が過ぎました。初めての経験の中、諸先生方には色々とご指導を賜り、何とか任期を過ごすことが出来ました。会長、副会長を始め理事の方々皆様のこの地域の医療に対する取り組みに真摯な思いを感じました。有意義な二年間でした。特に、この二年間はコロナの問題もあり大変だったと思います。理事になる以前は、医師会活動とは何をしているものかをよく理解していませんでした。医師会における私の主な仕事は、広報・情報システム担当です。ICT(情報通信技術)を利用したWeb会議システムの構築と年6回の安房医師会ニュースの発行、医師会ホームページの管理を行うことでした。医師会活動にいかに貢献するか。そのシステムの一員としてお役に立てればと思います。
コロナ感染が5月下旬になりようやく落ち着いてきました。安房医療圏では、GW前に連日50人近くの陽性者が出ていました。そのような中で「まん延防止等重点措置期間」が解除され、世の中はGWに突入。ニュースによると何も制限がないGWは3年ぶりとかで電車も飛行機も混雑したようです。ウイルスの弱毒化が言われていますが、感染者数、死者数ともに今回の第6波は今までの波の中で最多でした。全国的には、近頃の感染者数はピーク時の約1/5~1/6に減少しており、飲み会、集会も活発になっています。
昨年から、毎週或いは2週間に一回のコロナワクチン会議を安房医師会執行部と担当理事、安房保健所、三市一町の行政の担当部署など多くの職種の方で行っております。昨年11月、12月号の安房医師会ニュースの巻頭言でも言われているように、当地域は県内でも早い時期に高い接種率が達成されました。安房医師会員皆様の地域医療への高い意識の表れと思います。
日本の疫病の歴史を振り返ってみると、奈良時代の735年~737年に「日本で初めての疫病」である天然痘が大流行しています。仏教伝来の飛鳥時代6世紀頃に大陸から持ち込まれ、「天平の大疫病」として日本に拡がりました。死者は100万から150万人に上り奈良時代の朝廷の実力者の藤原不比等の4人の息子も全員天然痘で亡くなっています。治療法は現代で言う対症療法しかありませんでしたが、738年1月にはこの時の流行は、ほぼ終息しました。743年に聖武天皇は、国家の安泰を祈り東大寺の大仏や国分寺、国分尼寺の建立の詔、また墾田永年私財法の制定など、日本の政治と経済、および宗教に大きな影響を及ぼしました。
天然痘がコントロールできるようになったのは、江戸時代末期に蘭学とともに種痘ワクチンが日本に入って来てからです。内服薬はありません。種痘ワクチンは1796年英国の開業医エドワードジェンナーが、古くから行われていた人痘(天然痘)法よりも安全性の高い予防法として牛痘から開発しました。WHOは1958年に世界天然痘根絶計画を決議しますが、この時世界の発生数は2000万人、死亡数は400万人と推測されています。各国で、新たな感染者とその周辺の囲い込みで種痘ワクチンを行い、その効果が発揮され1980年5月に世界根絶宣言となりました。
コロナ禍においては、Go to事業や持続化給付金などの景気政策が行われています。また診療ではリモート診療、会社や団体ではリモート会議やリモートワーク、スポーツではリモートマラソンなどが出てきました。ネットの普及とコロナ禍により、いままでとは違う新たな生活様式が始まりました。一つの病気によって、今後も社会はどこまで変化するのでしょうか?
天然痘に人類が打ち勝ったのには、日本人の活躍がありました。熊本県出身の医師蟻田功氏です。WHO天然痘根絶対策本部長を務めた方です。彼の言葉を最後に紹介したいと思います。
「国は協力しあえるものだ。国際間には、紛争、戦争、無理解、憎しみ、差別、勢力争い、宗教の違い、政治の違いなど、色々な協力を妨げる問題があります。しかし、天然痘の根絶では、それらの違いを越えて皆が協力しました。」
現在の私たちを取り巻く世界情勢にも、必要な言葉ではないかと思います。
巻頭言 Vol.58 No.3 2022
巻 頭 言
安房医師会 理事 小林 剛
この原稿を執筆している4月上旬現在、国内の新型コロナウイルス感染者数は下げ止まり、第7波が懸念される状態にあります。世界に目を向ければロシアがウクライナに侵攻し、世界経済統合というグローバル化は半ば強引な形で終焉を迎えたと考えられます。他国に依存しない地域内統合へのシフトが本格的に始まるのではないでしょうか。まさに全世界が分断と混迷の中にある状態です。振り返れば2019年9月5日「令和元年房総半島台風」と名付けられた台風15号から安房地域での災害は始まっていました。復興に向けて踏ん張っている最中、2020年1月に武漢より新型コロナウイルスが国内にもたらされます。2月にはダイヤモンドプリンセス号を皮切りにして、以後長きに渡り未知のウイルスとの闘いを強いられることになりました。「1年延期からの東京オリンピック開催」という象徴的なイベントがあったにも関わらず、依然としてトンネルは暗く長く、出口は遠くにあります。わずかに光が見えているのか、それとも錯覚なのか目を凝らしている状態です。
新型コロナウイルスのパンデミックにより国内の死者は約3万人に到達しようとしており、医療介護現場では「災害医療」としての対応を余儀なくされました。確かに新型コロナウイルスにより人命が失われることは極めて遺憾なことです。しかし、このウイルスがもたらした最も大きな影響は「人間の生命が失われていく」ことよりも「人間のつながりが失われていく」こと、そしてそれに気がつかないことではないかと思っています。今まで当たり前であった、顔を合わせて素顔で笑いあうこと、共に食事を食べてお酒を飲み本音を語り合うことが簡単には出来なくなってしまいました。私たちはそれでも生きていくことが出来ますから、自らが意識しなければつながりは簡単に薄れてしまいます。無意識のうちに他者に無関心になり、ともすれば負の感情を抱きやすくなってしまう。新型コロナウイルス感染症による「社会学的視点から見た人間の変容」について、今後様々な解釈が生まれてくるでしょう。
それとは別に新型コロナウイルスは、止まらない東京一極集中という社会構造の中で、過度な人口密集の負の側面を教えてくれました。大都市では第5波時にほぼパニックと言えるほど医療の混乱を来していましたが、安房地域では幸い人口密度の低さに加え原 徹会長を中心とした行政との強固な連携体制、各医療機関の真摯な対応により在宅死者を出さずに乗り切ることができました。先日相模原市みその生活支援クリニックの院長である小野沢滋先生に「第5波で相模原市に起こったこと」をご講演いただきました。かつて亀田総合病院在宅医療部の部長をされていた小野沢先生に「安房は天国だ。あらゆる医療機関が地域の事を考えている。」と言って頂いたことを今でも覚えています。改めてこの地域で医療介護が出来るありがたさを感じ、会員の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。
医療介護を営むものとしてはこの上なく恵まれている安房地域ではありますが、この地域社会の全体を見てみると、生産年齢人口のみならず高齢者人口すら低下する「超高齢化過疎社会」の道を突き進んでいるのが現実です。教育、産業など地域の活性化に必要な変革は、はるか以前から求められています。移住者を含めこの地域で生活している様々な職種の方々がこの地域を活性化したいと奮闘しておりますが、中々大きな結果に結び付いていません。今後異業種の方との触れ合いの中から、地域活性化のために医療介護分野が出来ることを模索してみたいと思います。
最後に私が感銘を受けた航空会社ピーチの機内誌広告をご紹介させて頂き、結びと致します。少しでも早くこのトンネルから抜け、安房地域に火が、いえ炎が灯りますように。
「世界は驚くほど変わった。これまでのルールは過去のものになり、常識は非常識になった。けれど、大切なものは驚くほど変わらない。話す、笑う、触れる、感じる、愛でる。当たり前だったことが、どれほど貴重なことかを痛いほど感じることができた。だからこそ私たちは大切にしたい。距離に負けることなく、顔を合わせて話すこと、五感で楽しむこと。心の赴くままにリアルな体験を重ねること。私たちは、考える。画面越しにつながれる時代だからこそ、リアルな価値は高まっていると。アタマよりココロが求めるものを、画面を隔てては味わえない驚きを届けたい。逆風を恐れず進もう。向かい風が強いほど、高く飛べるのだから。」
巻頭言 Vol.58 No.2 2022
巻 頭 言
安房医師会 理事 福内正義
今回巻頭言を担当させていただきます病診連携担当理事の福内です。コロナ禍になり3度目の冬を迎えることになりました。この2年間で生活や会議の様式、働き方等様々な変化があったと思います。コロナウイルスは人から人への感染が唯一の伝播方法であり、デジタルデバイス等を通じて感染することはありません。国も電話再診やオンライン診療を推奨しています。私の勤務する安房地域医療センターでもデジタル化がだいぶ進み、ほとんどの会議や講演が対面とwebのハイブリッド方式で行われるようになりました。ちなみに安房医師会の理事会もハイブリッド方式でおこなわれております。
さて皆様は北京オリンピックをご覧になりましたか。おそらく全くみなかった人のほうが少数派ではと思います。一日あたりのコロナ感染者数が日々更新というなか2月3日に北京オリンピクの開幕をむかえました。この原稿は2月初旬に書いており、今大会日本人第一号のメダルをスキーモーグルの堀島行真選手が獲得したという朗報もありました。
今回のオリンピックを観ていてスポーツの世界でもデジタル技術の進歩を感じます。スキージャンプ競技では複数台のカメラで着地までの距離を正確に計測し、また風速や風向に応じて加点や減点が自動的に行われます。フィギュアスケートでは6台のカメラをリンク周囲に設置してジャンプの高さや距離をリアルデータとして測定しています。この技術は前回の平昌から導入されているようです。また、今大会はじめてスピードスケートのスタート時のフライング探知に、画像追跡システムが活用されるようになりました。このような技術は、まだ特殊で高価なものかと思われます。将来的により簡単に多くの人が利用できるようになれば、オンライン診療等にも活用できるのではとおもいます。私は整形外科が専門ですので関節の動きや四肢の変形、腫脹などが、オンラインで画像解析できれば、かなり正確な診断ができるのはと考えております。もちろん内科的な疾患等に関しては、画像解析だけでは診断できないものも多くあると思います。
海外の整形外科では初診からオンラインを導入し、患者さんは医師やPA(フィジシャンアシスタント)の問診をうけ、必要な検査のみを病院に受けにくるといった事がはじまっています。検査結果を再度オンラインで説明し、手術が必要となったら術前説明をオンラインで行い入院日を決定する。そして入院日に初めて担当医と対面するといった流れのようです。オリンピックで使われているデジタル技術が応用できればさらに診断が正確になり、術前に行う検査を減らすことができるかもしれません。
オンライン診療は自宅にいながら診察をうけられ、とくに移動手段がすくない高齢者にとっても都合の良い面が多くあると思われます。もともとデジタルデバイスにあまり慣れていない高齢者にどうすすめるかなどまだ課題はありますが、高齢化のすすんでいる安房地域でもメリットは大きく、今後の拡大に期待したいと思います。
巻頭言 Vol.58 No.1 2022
巻 頭 言
安房医師会 会長 原 徹
令和の和暦も既に3年が過ぎました。この間、災害や感染性疾患などが発生し、平時とは些か対応が異なる事案が重なりました。このため本組織の運営面でも不安と戸惑いが拭いきれない状態が続きましたが、それでも何とか組織活動を維持することが出来ました。その礎となったのは“地域住民をはじめとして関係諸機関の皆様、そして会員ならびに役職員諸氏のご理解ご協力である”と心から感謝しております。この様な混乱期に事務局の転居も重なり、さらに毎週の様にコロナ対策等の話し合い、各種会合・調整も行われましたが、この難局を乗り越えることにより安房地域での職域間、組織間の連携が従前よりさらに円滑、ならびに強固になったと感じています。翻って昨年11月には一旦、急激に新規感染者数が減り安心していましたが、残念な事にその直後に新たな変異株が出現、海外からの入国が全面的に制限された状態にも陥りました。そんな中で一番大切なものは人々の精神面での安寧・不安の払拭ではないかと感じています。顔の見える連携・意思疎通があれば不安を減じた状況下での相談や依頼も容易であり、一方医師会からの支援・協力も円滑に行うことが可能となると思います。
ところで皆様は何を拠り所・生き甲斐にされていますか?度重なる不安や危機から“生きる目標”を失っていないでしょうか?こんな時代に“欲”を持つことは品が無い事と言われそうですが、私は今こそ“欲”を掲げ前進する時だと感じています。現在放映されている朝ドラ・come-come-everybodyの主題歌名は【アルデバラン】、これは“おうし座”のα星の名前で、アラビア語では「後に続くもの」の意味だそうです。同じ“おうし座”のスバル【プレヤデス】の後を追う星であり、冬の夜空で“おうし”の目の部分に位置し、赤橙色に輝いています。その歌詞の一部を年始にあたりここで紹介させて戴きます。
『きみと私は仲良くなれるかな? この世界が終わるその前に きっといつか儚く枯れる花 今、私の出来うるすべてを 笑って笑って愛しい人 不隠な未来に手を叩いて 君と君の大切な人が幸せである そのために祈りながらsing a song 』(森山 直太郎 作詞・作曲)
新年に私の掲げる“欲”は『関係する愛しい人々に笑ってもらい 不隠な未来にも屈せずに大切な人々が幸せになること』です。これを本年の大きな“目標・欲”として掲げて活動したいと思います。
煌めくアルデバランを見上げて・・・・・。
巻頭言 Vol.57 No.6 2021
巻 頭 言
コロナ禍における安房医師会のチーム力
安房医師会 理事 原太郎
コロナ禍から見えてきた医療体制の課題
デルタ株による新型コロナ感染症が猛威を振るった今夏、しばらく静かであった安房地域においても感染者は爆発的に増加し、都市部では医療体制の崩壊から多くの在宅死を招いた。その後、ワクチン接種が進み「第5波」は一旦収束したが、新型コロナウイルスによる非常事態は国や自治体が抱える様々な課題を浮き彫りにし、組織のリーダーや、それに関わる組織の能力が一層問われるようになった。国のコロナ対策をみると政府と自治体、厚労省などいくつもの指令系統が併存し、統一された方策が示されない状況の中、感染対策やワクチン接種において、現場が難しい判断を迫られる場面もあった。千葉県の体制をみても県医師会、千葉大学病院、県立病院、民間病院の医療連携体制は十分とは言えず、危機管理において、司令塔の一元化、医療体制の整備が極めて重要であることを今回再認識した。
コロナ禍における安房医師会の活動
今回のコロナ禍において、安房医師会は、会長を中心に執行部、各担当理事、医師会員が一丸となり、感染対策からワクチンの接種体制の構築、クラスター発生施設の医療支援、在宅療養者の管理体制の構築へと常に地域医療のために迅速かつ献身的な活動を行ってきた。コロナを巡る様々な問題は、週単位、時には日単位での対応を迫られる厳しい状況であったが、安房医師会では整った医療連携体制と一元化された指示系統によって臨機応変な対応が可能であった。
安房医師会の強みは、理事が亀田総合病院、館山病院、安房地域医療センターなどの地域の基幹病院とクリニックの医師で構成されており、有事に際しては、医師会を中心として司令、統制が一元化されていることにある。そのため、コロナ禍においても地域の医療を支える各医療機関が常に連携し、協力体制が構築できた。そして、安房医師会のもうひとつの強みはチーム力にある。安房医師会の活動は会長、執行部が先頭に立って行っているが、決してトップダウンではなく、皆が自由に意見を出し合い、理事それぞれが担当分野を超え協力し、チームとして動いている。非常時にはチーム内での情報共有が必要不可欠であるが、今回のコロナ禍では、これまでのメールや電話による情報交換だけでなく、各理事がラインを通じてリアルタイムに情報を共有することが可能となり、様々な状況下で迅速な対応に繋がった。医師会ラインでは日々のコロナ感染状況やワクチン供給体制、各会議の内容、時には身近な話題や日常の写真など、一定のルールのもと、意見を発信することができる体制にあり、医療情報の共有だけでなく、それぞれの理事の意外な人柄や思考を知るきっかけにもなった。非常事態時にはラグビーのone for allの精神をもったチーム力が大切であるが、安房医師会はコロナ禍を経験したことで、互いに協力し合う精神が培われ、より強固な組織力を得たと感じている。
行政との地域医療連携体制
非常時の医療体制には行政との密な連携も極めて重要である。安房地域では、コロナ感染の拡大以降、行政を交えてコロナ対策会議を毎週開催してきた。会議には安房医師会執行部、理事の他、4市町の行政、保健所職員など多くの職種の方々が参加する形で、ワクチン接種の体制作りから在宅療養者の管理方法まで、ひとつひとつの問題点について議論を交わし、解決策を講じてきた。コロナの感染状況やワクチンの供給状況が変化する中で、多業種が連携するということは一筋縄ではいかないこともあり、行政と医師会で対応をめぐって意見がぶつかることもあったが、それぞれの立場の違いを理解し、常に行政の意見も交えて協議を重ねてきた。このコロナ対策会議を通して医師会、行政間でお互いに顔の見える関係が築かれ、強固な連携体制が形成されたもの確信している。現在の安房医師会が全国地区医師会のなかでも組織力の強い素晴らしい医師会になっていることを誇らしく思うと同時に、この安房医師会は先人の理事、会員の努力によって発展し、引き継がれてきたものであり、敬意を表したい。
これからの安房医師会の役割
新型コロナウイルス感染症という非常事態は、地域医療のあり方、医師会という組織の重要性を改めて考えさせられるものであった。コロナ禍と異常気象の中で、地区医師会が担う役割は益々増えていくものと思われる。非常時には地域の基幹病院、行政との連携は必須であり、今回コロナ禍で培ってきたチーム力を活かし、長期的なビジョンを持ちつつ、状況に応じて柔軟に対応できる地域医療体制を整える必要があると考えている。自然豊かな安房の住民の健康を守り、皆が不安なく安心して暮らせる地域社会を作ることが我々安房医師会の役目であり、私自身の原動力にもなっていると今は強く感じている。